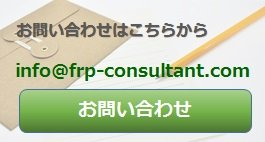波、風、陽による同時発電を行うNoviOceanの発電システムとFRPの適用
今回は波、風、陽による同時発電を狙うNoviOceanの発電システムとFRPの適用について述べたいと思います。
環境保全に関する事業は資金が集まりやすい状況
事業性という意味だけでいえば、
環境保全に関する事業は課題が多いのが実情です。
一方で社会的な関心の高さから、
創業時からお金が集まりやすい傾向にあるようです。
可逆的なプロセスを軸にしたReverionは、環境保全という観点で注目される企業の一つだと思います。
当該企業については、私が偶然目にした海外のニュース番組で取り上げられていました。
特徴は小型ユニットのため設置の自由度が高いこと、
そしてバイオガスで発電するだけでなく、
余剰電力を使って水素などを生成させて保存するといった、
可逆的なプロセスが可能であることにあります。
詳細は以下のような日本語のHPで読むことができます。
※参考情報
高効率で可逆的カーボンネガティブ発電所(TECHBLITZ)
まだ利益を出せるような状態ではないようですが、
昨年9月時点で6200万ドルの資金を集めたと上記の記事に記載があります。
日系企業も出資しているようです。
まずはドイツを中心とした欧州からのようですが、
製造キャパシティー向上に伴い、日本でも導入される可能性があるでしょう。
このように事業性への期待だけでなく、
より広い視点での課題解決という意味で資金が集まる状況にあると感じています。
次にFRPに関係するもので、環境保全技術に取り組む企業の製品をご紹介します。
波、風、陽を組み合わせた発電機構を提案するNoviOcean
JEC Composite Magazine 164(Sep-Oct 2025)内の記事でも紹介されていたのが、
波、風、陽を組み合わせた発電機構を提案するNoviOceanです。
2025年時点では1:1スケールによるSTAGE4(TRL7)という実機検証の段階にあり、
本格的な上市は2031から2032年ころになるようです。
こちらも注目を浴びている企業のようで、
3,000万スウェーデンクローナ(約280万ドル)の助成金を獲得した、
という記事が数週間前(2025年9月初旬)に出ています。
※参考情報
以下、要点を述べます。
機能性を組み合わせるというコンセプト
私自身も重要だと考える”複数の技術”を組み合わせる、
ということを軸にしているところが大変好印象です。
この辺りは以下の動画を見るとわかりやすいかもしれません。
複数の発電機構を一体化することで構造もシンプルになり、
コスト抑制はもちろんですが、それ以上に私がメリットと思うのが、
「異なるエネルギー源によってお互いの発電量を補える」
ということでしょうか。
波動による発電は比較的安定している一方、
天気がよくて風が穏やかだと風力発電は難しく、
それを太陽光発電で補えるといったものが一例です。
波力発電では共振させないことで発電を安定化させようとしている
波力発電に関して”共振させない”ことがコンセプトとして重視している旨、
JEC Composite Magazineの記事に書かれています。
合計14個の”可動式の浮き”がついており、
この浮きは規定圧力に到達しないと動かない設定となっているとのこと。
こうすることで大きさや周波数が変動しがちな波に対し、
ある一定以上の振幅の波を”いなす”効果が得られるとのことです。
波力発電については、一日当たり21トンの荷重として一万回発生する波による力を、
流体によって圧力に変換してタービンを回して発電する仕組みです。
詳細は書かれていませんがこの発電機構一つあたり300kwの波力発電由来の電力を生みだせるうえ、
40年の製品寿命を想定しているようです。
波力発電については、過去にも取り上げたことがあります。
※関連コラム
FRPの適用は波力発電向けの浮きや筐体の外殻構造、そして風力発電ブレードに使用
FRPが適用されている個所について述べます。
浮きの発泡剤の外殻構造にFRPを適用
発電機の主構造である筐体や前出の波力発電に用いる浮きについては、コア材としてEPS(ビーズ法ポリスチレンフォーム)やXPS(押出発泡ポリスチレンフォーム)を用い、その外側をFRPで被覆する構造のようです。
FRPについて詳細は書かれていませんが、
ガラス繊維を用いているとのことでGFRPであるとは明らかにされています。
筐体と浮きの総体積は300m3とのことで、相応のサイズです。
よってGFRPを含めて使用する材料量も大きいと考えられます。
外殻を補修することによる再利用が可能であることも確認
長期耐久性試験において劣化した後は、
(恐らく劣化箇所を)部分的に除去したうえでFRPで外側を再度FRPで被覆することで補修し、
そのまま再利用できることも確認したとのこと。
発電機構として40年は維持させたいという狙いに対して、
FRPの補修は不可欠ともいえるでしょう。
賦形性の高いFRPの特性を活かした補修については、
過去のコラムでも何度か取り上げています。
※関連コラム
FRP製電柱の拡大と既設電柱のFRPによる補修・補強の重要性
FRP戦略コラム – 日本の 航空業界 発展に必要な非破壊検査と補修事業
風力発電ブレードに用いるFRPについて詳細記述は無し
”風力発電ブレードにもFRPが使われている”という記述は有りますが、
どのような材料を使用しているかといった詳細の情報は全くありません。
コスト考えればGFRPの可能性が高いですが、
サイズを小さくして回転数を稼ぎたいという場合、
遠心力による変形を防ぐため弾性率を高くする設計思想によって、
炭素繊維を用いたCFRPを部分的に用いていることも否定できません。
FRPについてはリサイクル性に関する懸念に言及
NoviOceanはFRPが海水に対する耐腐食性を有することなどを引き合いに、
当該材料の適用に前向きであることを述べています。
ただ懸念として述べられているのがリサイクル性。
長寿命に加えてリサイクル性まで担保できれば、
より積極的にFRPを使用したいということだといえます。
GFRPのリサイクルに対する要求は、
何年も前から私も述べている通り急激に高まりつつあるといえるかもしれません。
※関連コラム
Glass Fiber Europe が示した自動車向けGFRPのリサイクルに関する指針
FRP製風力発電ブレード驚きの廃棄量予想と求められる取り組み
この記事から考えるべきことについて私見を述べます。
遠隔でのヘルスモニタリングが求められる
今回紹介した発電システムは”安定稼働”することが前提となっています。
発電はインフラの一種であるためです。
よって、FRPを含む構造部材の損傷やその前兆、
そして通信機器の故障についても同様の事象を検知する必要があります。
まさにヘルスモニタリングが不可欠となるでしょう。
常に波力や風力による外的荷重がかかる使用方法のため、
前出の構造部材や通信機器の故障リスクも高いものと考えます。
このように繰り返しの荷重付加環境下での安定稼働を手助けするセンシングシステムは、
これからニーズが高まっていくでしょう。
※関連コラム
アコースティックエミッションを TypeIV の高圧タンク品質管理に採用
風力発電ブレードの更なる形状進化
風力発電ブレードも関係する”空力”の世界は、
CFD(Computational Fluid Dynamics:数値流体力学)の進化によって、
技術が前進している技術業界の一つであると認識しています。
結果、様々な新しい形状の受風機構の提案がなされています。
NoviOceanのブレード形状も一般的な風力発電ブレードとは異なる形であることが、
各種動画や画像から読み取ることができます。
過去のコラムでご紹介した垂直型マグナス風力発電機や、
縦渦リニアドライブはその一例です。
※関連コラム
船舶の燃費改善に効果があると期待されるFRP製 Rotor Sail
風力発電を行う受風機構について、
- できるだけ小型で軽く
- 少ない風力で安定して回転(もしくは他の運動)できる
といった複数の技術的要件を両立させる形状に関する研究開発が、
今後さらに進展するものと考えられます。
最後に
クリーンエネルギーや再生可能エネルギーによる発電には、
FRPが何かしらの形で関係していることが多いです。
軽く、耐腐食性があるという特性をうまく活用していることがその背景にあります。
ここでネックとなるのが材料のライフサイクル。
リサイクルがやりにくいということが、
今回のNoviOceanの話の中でも触れられていました。
まず必要なのはGFRPのライフサイクルの構築です。
既に私の知っている範囲でも取り組みは始まっているので、
後はそれがより周知され、かつスケールアップして実際に活用される場面が増え、
結果として一つの産業に発展していくことを期待したいと思います。