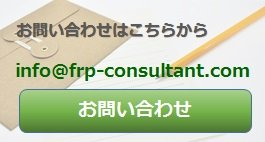非加熱硬化プリプレグGF-NCF/UV-cure-resinによる補修
FRPは強化繊維とマトリックス樹脂を組み合わせた複合材料であり、
通常、マトリックス樹脂は熱硬化または熱可塑です。
つまり、熱を媒体として硬化反応が進行する、
またはガラス状態からゴム状態に相転移することで、
FRPとしての成型(成形)工程を実現しています。
これらと少し毛色の違うマトリックス樹脂が、
「非加熱硬化タイプ」
です。
非加熱硬化タイプは今回取り上げる紫外線硬化だけでなく、
可視光硬化や電磁波で硬化(または低分子化)するタイプもあります。
これに関連したものは過去のコラムでもご紹介してます。
※関連コラム
電磁波による離脱可能なイオン液体添加 アクリル接着剤 の研究
Stuttgart大学でUV硬化FRPの研究プロジェクト開始
今日はこの中で紫外線硬化樹脂をマトリックスとした、
GF-NCF/UV-cure-resinプリプレグを用いた補修への応用についてご紹介します。
なおGFはガラス繊維、NCFはNon crimp fabric、UV-cure-resinは紫外線硬化樹脂を指すものとします。
GF-NCF/UV-cure-resinプリプレグを用いた補修
金属パイプをGF-NCF/UV-cure-resinプリプレグで補修する工程を示した動画があります(音が出ます)。
この動画を見ていただくと、
GF-NCF/UV-cure-resinプリプレグを用いた補修のイメージがつくと思います。
ポイントを述べます。
穴の開いた金属パイプにGF-NCF/UV-cure-resinプリプレグを巻き付けることで補修
補修は損傷領域をGF-NCF/UV-cure-resinプリプレグで被覆した後、
紫外線で硬化させるというものです。
今回の補修対象は金属製のパイプですが、
後でご紹介する通り風力発電ブレード、船体といった産業用途や、
詳細は不明ですが防衛製品にも使うことを想定しているようです。
防衛については例えば過去にも紹介した防弾向けが想定用途のひとつかもしれません。
※関連コラム
FRPとCMC/MMCを用いた軍用車両向け装甲防御材の防弾性能評価
表面を粗した後、洗浄とプライマー塗布が必要
表面を研磨後、洗浄してプライマーを塗布しています。
ここから考えられることは、無機材である金属との接着性はあまりよくないということです。
プライマーはカップリング剤などが含まれていると推測され、
FRPと金属間を結び付けるものがアンカー効果に加え、
化学結合の生成が必要なのだと思います。
カップリング剤に関連する表面処理として、
POSSをご紹介したことがあります。
※関連コラム
かご型シルセスキオキサン(POSS)で表面処理したGrapheneのFRP製スキー板への適用
またカップリング剤というとシランカップリングをイメージすることが多いかもしれませんが、
ケイ素の代わりにチタンを使ったチタンカップリング剤もあります。
シランカップリング剤と比べ、チタンカップリング剤は触媒が不要で、反応が早いという特徴があります。
※参考情報
プリプレグは2層のフィルムで被覆されている
画像を見ていただくと黄色のフィルムが見えると思います。
これは紫外線吸収効率が高い黄色で外光遮蔽することで、
不要な硬化進行を防ぐことが目的です。
さらにその下にもう一枚透明なフィルムがあり、
これはローラで脱泡する際、
材料がローラ側に樹脂や材料が付着することを防ぐためのものです。
硬化時間は動画の例でおよそ5分
後半ではブラックライトを当てることで硬化させています。
時間は5分ほどとのこと。
一か所当てれば全体が硬化するわけではなく、
位相を変えてライトを当てていることが分かります。
次にプリプレグについてもう少し見ていきたいと思います。
GF-NCF/UV-cure-resinプリプレグの概要
今回動画をご紹介したのはSunrezという企業のプリプレグです。
材料について細かくは記載されていませんが、
以下のようなサイトが存在します。
Sunrez Products / Curing at The Speed of Light
これを見るとプリプレグに用いるマトリックス樹脂は7355という一種類で、
組み合わせる強化繊維が複数あるのが分かります。
後述するNCFの作り方含め、
以下のような動画で概要を見ることができます。
ここでは風力発電ブレードの補修に当該プリプレグを使う、
というコンセプトになっています。
強化繊維はNCF
強化繊維はガラス繊維のNCF(Non crimp fabric)を主としており、
+45/-45を組み合わせたBiasの800gsm目付、
同UDの1000sgm、多軸の900gsmがそれぞれあります。
ここでいうUDは一般的にいうUDとは異なり、
繊維配向の垂直方向にばらばらにならないよう、
ステッチで固定しているNCFであることに注意が必要です。
NCFは元々風力発電ブレードのような大型で複層積層が必要な構造物向けに開発された強化繊維形態で、
今では航空機部品や土木建築、自動車の部品など様々なところに用いられています(強化繊維はガラスだけでなく、炭素繊維の場合もあり)。
作り方については前出の動画の1’11″付近から見ることができます。
配向を持ったガラス繊維を編むわけでも織るわけでもなく、
”設置する”状況が分かると思います。
この後工程でステッチすることで複数の層/配向を有する強化繊維を固定します。
樹脂を含浸させ、プリプレグ化する様子も映っています(1’07″付近)。
なお、NCFについては過去にも取り上げたことがあります。
※関連コラム
KTM がFMC/NCF/elastomerでSkid plateを開発
FRP学術業界動向 – NCF を用いた 風力発電 ブレード製作自動化検討
FORMAX が Advanced Engineering UK で NCF 基材を発表
また、NCFについては日本国内でも製造販売する企業があります。
※参考情報
マトリックス樹脂はラジカル重合系と考えられる
7355という樹脂は低VOCであるという情報しかないため詳細は不明ですが、
Sunrezの有する樹脂のラインナップを見ると、
ビニルエステル(エポキシアクリレート含む)、不飽和ポリエステルと書かれており、
このことからラジカル重合系であると考えられます。
ビニル基であるCH2=CH-の結合があるというとわかりやすいかもしれません。
同じ光硬化でもカチオン重合のエポキシと比べて圧倒的に硬化が早いのが特徴です。
歯の治療に使われる光硬化性樹脂もメタクリレート系樹脂であることが多く、
これもビニル基を有する化合物になります。
光重合を進める開始剤は複数ある
光重合による硬化反応を始めるには開始剤が必要で、
この開始剤である分子の開裂などでラジカルが発生することで連鎖反応が始まります。
開始剤はベンゾイル基(Ph-CO-)を有するものを中心に様々な種類が存在します。
黄変が少ないもの、水溶性のもの吸収ピークがより短波長のものが一例です。
以下の参考情報によると吸収波長は380から440nm程度のようです。
※参考情報
SunrezのプリプレグもUV-Aで硬化するとのことで、
硬化に用いられる光の波長は300から400nm程度の範囲にあるものと考えられます。
今回の情報から考えるべきことについて述べます。
光硬化性樹脂は熱硬化のものと比べ特性値が低くなりやすい
これは私の古い記憶でしかないので今は違うのかもしれませんが、
光硬化性樹脂は熱硬化性樹脂と比べ硬化物の機械特性が低い印象があります。
より具体的には脆性材料であり、壊れやすいイメージです。
今回のプリプレグも材料特性には一切触れられておらず、
熱硬化性のものと比較しての違いが分かっていません。
熱が不要なのは魅力的ではありますが、
硬化物の特性が求めるものに達しているかの確認は必要でしょう。
品質安定性の懸念
これは熱硬化でも同じですが、
硬化反応が終わっていない材料の品質保証は本当に難しいです。
Sunrezのインタビューが以下の動画で見られますが、
この辺りの話も出ています。
製造段階で開始剤の吸収帯である光に触れないようにすることが重要とのこと。
一方で水分が硬化に悪影響を与えないのか、
といった話も出ていましたがそれについては影響はないというSunrezの回答を確認できます。
紫外線はガラス繊維を透過する
当たり前といえば当たり前ですが、
紫外線はガラス繊維を透過できるので、
複数層積層した後に外層側から光を当てることで硬化物を得ることができます。
これがもし炭素繊維のように黒いと難しいでしょう。
既述の通りパイプの補修では複数の方向から光を当てる様子が映っていました。
Sunrezのインタビュー動画の中でも、
光の拡散に伴い深さ方向に対する多少の硬化領域拡大は期待できるが、
硬化が進むのはあくまで光の当たった領域近辺に限られるという発言があります。
ラジカル硬化反応は連鎖反応ではありますが、
停止反応など複数の反応との競合となります。
きちんと硬化させるには全面に、
適切な波長かつ光量を材料に供給することが不可欠だと考えます。
サイジング剤の影響は無視できない
今回ご紹介した情報内では全く出てきていませんが、
ガラス繊維表面に塗布されたサイジング剤が、
紫外線硬化(光硬化)反応、つまり光開始剤で始まったラジカル重合反応や、
その硬化物に何かしらの影響を与える可能性があります。
サイジング剤はガラス繊維の種類によってさまざまであり、
仮に不飽和ポリエステル系といってもそこに含まれるカップリング剤をはじめとした、
様々な化合物の存在は無視できないでしょう。
マトリックス樹脂を選定する際は、
そこに組み合わせる強化繊維との相性を見ることも重要です。
まとめ
今回は非加熱硬化システムのプリプレグをご紹介しました。
紫外線硬化を補修に用いようというコンセプトは斬新というわけではありませんが、
材料側の進化に伴ってその適用範囲が広がってきた印象は受けます。
Sunrezのインタビュー動画中では熱硬化性の従来材と比べ、
紫外線硬化のプリプレグはやや高価であると述べられていますが、
できるだけ早く補修を終わらせたいというニーズに対しては合致しており、
また作業者の拘束時間を踏まえると材料費だけに着眼したコスト議論は現実的ではないのかもしれません。
そしてFRPの主役といえる”ガラス繊維”が主体となっていることも注目すべき点です。
FRPというと炭素繊維というイメージが強い方もいるようですが、
ある程度量を見るのであれば生産許容量や調達安定性の観点からも、
ガラス繊維に目を向ける必要があるでしょう。
※関連コラム
FRP製電柱の拡大と既設電柱のFRPによる補修・補強の重要性
建築物のFRPによる補修後の検査方法に関する新しい規格 ASTM WK74694
接着補修やFRP硬化・加熱時の 内部温度 計測に対する新しいセンシング