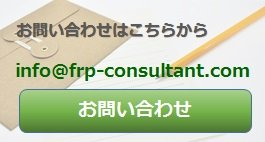High Altitude Pseudo-Satellite/HAPSの一次構造材へのFRP適用
高高度無人飛行機とも呼ばれるHigh Altitude Pseudo-Satellite(HAPS)と、
その一次構造材にFRPを用いることについて取り上げたいと思います。
HAPSとは
高度2から5万メートルほどを飛行する無人飛行機で、
データ通信を行える移動基地といったイメージでしょうか。
HAPSの技術要素を理解するにあたっては、
以下のHPが分かりやすく解説していましたので、
こちらを参考にポイントを述べてみたいと思います。
※参考情報
HAPS Research Group / The University of Tokyo
HAPSの意義
人工衛星と無人航空機の強みを兼ね備えたものと言っていいでしょう。
HAPSの活用法については、以下の動画が分かりやすいと思います。
日本だけでなく、開発途上国や巨大な国土を抱える国の通信網構築を実現する選択肢の一つと認識されています。
SoftbankのHAPSに用いている機体はAeroVironmentと開発したSungliderです。
2024年10月の段階で成層圏での飛行を成功したとリリースが出ています。
※参照情報
ソフトバンクのHAPS向け大型機体「Sunglider」がAeroVironmentと米国国防総省が実施した実証実験で成層圏飛行に成功 / Softbank
HAPS Research Groupにおける主たる研究要素
HAPS Research Groupにおける研究の現段階のゴールは、季節と緯度によらず24時間(日照が無い環境で12時間)飛行できる、つまり一年を通じて永続飛行をできる機体を得ることにあります。
その実現に向け、設計、構造、回路、制御、太陽光発電/電池が重要な研究要素と述べられています。
それぞれの概要に触れます。
設計
主に形状設計のことを指しています。
飛行中の機体に対する抵抗を減少させることが最重要のようです。
前方投影面積の減少と揚力分布を楕円分布に近づけることで、
それぞれ有害抵抗と誘導抵抗を抑えることを目指しています。
空力解析や応力解析を行いながら形状最適化を目指しています。
本点については発表されている技術資料をもとに、
この後、もう少し中身を見ていきたいと思います。
※関連コラム
構造
FRPに関連する部分です。
軽量かつ小抵抗を維持しながら、
組み立てや修復のやりやすいという運用の容易さの両立を目指しているとのこと。
構造材は主として木材を用いているとのことですが、
ウレタン(充填と書かれているので恐らく発泡ウレタンのこと)やFRPも用いているとの記述があります。
加えて地上での機体設置や試験、メンテナンスを行うことを目的に、
治具を作るといったことも行っているようです。
回路
基板は胴体に複数搭載され(当該機体は複数の胴体があるため)、それぞれがコネクタによって通信をしており、その通信でやり取りしたデータをもとに、機体全体の姿勢の推定や飛行進路の決定と、スロットルや動翼の出力指令を出すことが役割とのことです。
構造設計と解析の結果に近い動きをできるよう、
適切に機体を動かすためのインフラ構築が使命と理解しました。
最新のGen5ではセンサとログ取得、姿勢補正と機体誘導を行うマイコンをそれぞれ搭載し、
また基板間通信に関して多対多通信に変更するなど、
小型化と性能向上を狙っている、という記述もあります。
制御
自動操縦と地上局での監視を行うためのアルゴリズムやソフトウェアの開発を行っているとのことです。
自動操縦では能動空力弾性制御という主翼のねじり変形を活用した空力特性最適化をリアルタイムで行うという、複雑な構造変化と空力性能最適化を両立させる制御技術を導入しているようです。
太陽光発電/電池
ソーラーパネルが発電する際に出力電力を最大化する制御回路を中心に、
当該発電システムの開発を協力企業と進めていると書かれています。
太陽光発電に関しては空力性能向上を実現する主翼形状に合わせてソーラーを搭載すること、
そして重量的なデメリットを生じさせないこと、
さらには電池についてはエネルギー密度の高いリチウムイオンバッテリーのパック開発に着手する、
といった取り組みが述べられています。
※関連コラム
次にHAPS Research Groupにおける構造設計に関する研究例に触れます。
HAPS Research Groupの研究例
参考にしたのは以下の発表です。
※参考情報
森田直人,土屋武司, 非構造パネル法による効率的な動安定微係数・舵効き推定手法の提案とフライトシミュレーション環境の構築, 61回飛行機シンポジウム,Nov. 15-17,2023,北九州
数理最適化技術と機体空力解析を組み合わせ、
長時間の飛行を可能にする期待形状とバッテリー重量を見出し、
得られた結果を用いて24時間飛行を実現する機体の基本仕様を決める、
というものです。
ポイントをいくつか見ていきます。
翼幅の拡大に伴う抵抗と機体重量の変化から必要な翼幅を予測
HAPSは省エネで長期間飛行するにはどうすべきかを最重要視しており、
基本構造設計思想として、重量を抑制しながら翼幅を拡大するのが定石です。
イメージを理解するには以下の動画をご覧いただくといいかと思います。
参考情報の論文1ページ目右下から2ページ目にかけて最適化に用いる計算式を見ると、
その重量評価に主眼が置かれていることを理解できるかと思います。
上記の重量計算式で求められた重量をベースに、
揚力係数や有害抵抗係数、そしてバッテリーやプロペラなどの効率、
さらにはバッテリーのエネルギー密度といった数値を導入し、
「太陽光が無い状態でもどのくらいの時間飛び続けられるか」
という超過飛行時間Texcessを示したのが、同論文2ページ目右側にある式になります。
結果の概要が当該論文の図2に示されており、
翼幅が大きくなるほどTexcessが大きくなり、
24時間以上飛行するには今回の基本条件下だと6.7m以上の翼幅が必要であるのが分かります。
空力性能を考慮し、機体の消費電力を予測
予測には遺伝的アルゴリズムというものを用いているとのこと。
先尾翼(カナード)の幅と長さ(論文中 図6)を含む複数個所の翼断面形状を含む機体形状から、
バッテリー重量は5から8kgの範囲にする必要があることを明らかにし、
特定の地点と高度における日照時間の実績から、
約7kgが最適であるとの結果が導かれています。
さらにバッテリーの最大容量の80%程度までしか使えない、
ソーラーパネルの搭載面積と日の出日の入りによる太陽光の斜角といった追加の条件を考慮し、
それでも24時間以上の飛行が可能であることが示されたとのこと。
解析が非粘性を前提としていること、胴体形状を考慮していないことといった課題が示されているものの、個人的には丁寧な計算をしていると感じています。
次にHAPSの構造部材としてFRPを使うことについて考えます。
HAPSではアスペクト比が大変大きい構造のためFRP適用意義がある
ここまで述べてきた通り、HAPSの翼は大変細長い形状、
つまりアスペクト比が大きくなります。
このような構造では”比弾性率(比剛性)”が大変重要です。
比重当たりの弾性率(合成)が高いということは、
細長い形状にしても変形しにくいからです。
そのためこのような構造材には、
比弾性率の高いFRPが多く用いられます。
前出のHAPS Research Groupでの計算でも、
- 主翼カーボンパイプ
- 胴体のカーボンパイプ
という単語が見られ、
CFRPの中空パイプが用いられていることを示唆しています。
中空パイプで最も一般的な作り方は手巻き
これは意外と思われるかもしれませんが、
中空のCFRPパイプを作る最も一般的な作り方は”手巻き”です。
主にUDや織物のプリプレグを手でくるくると巻き付けるイメージです。
この作り方はFRP適用で歴史の長いスポーツ業界でよく見られます。
以下の動画はその一例です。
材料(マトリックス樹脂と強化繊維を一体化したプリプレグ)の裁断から積層、ラッピングの後のオーブンでの硬化、さらにはカットや塗装までの一連工程が示されています。
この中で技術的には最も重要な工程の一つである積層作業は人の手で行われています。
また、様々なカットパターン(材料の裁断形状)の材料を用いることで、
狙いの構造物の形状に加え、特性発現するよう調整されていること動画で見ることができます。
このような手作業による積層は非効率と見る方もいるようですが、
人の手による積層は大変品質が高く、
FRPの世界からなくなることは”絶対に無い”と考えています。
私自身も北米でのFRP量産工程立ち上げの際、
手作業による積層で品質を底上げした経験があり、
どれだけ自動化の技術が進化しても成形体の品質という観点では人の手にはかなわないでしょう。
課題と見るべきは、このような作業の専門家の高齢化と減少だと私は考えます。
強化繊維の選定に加え、積層配向や積層構成で材料の示す剛性は変化する
ここがFRPの特性として重要視すべきことだと思います。
CFRPを中心に使用する材料は連続繊維が強化材になります。
連続繊維の繊維配向は成型後の構造物の剛性に大きな影響を与え、
かつその剛性には”異方性”があります。
例えば中空パイプを一例として、
長手方向に強化繊維を多く配向させれば非常に曲がりにくいパイプとなります。
ここに長手方向に対してある程度の角度をもって繊維の配向を変えれば、
徐々に曲がりやすい構造部材となり、その配向角度によって曲がり方も調整できます。
材料を積み重ねる”積層”というFRP特有の考え方故、
積層構成、すなわちどのような順番でどのような材料をどの配向で積み重ねるかによって、
成型後の構造部材の剛性を変化させることも可能です。
今回事例として示したHAPSでも述べられていましたが、
主翼が全く変形しないのではなく”ねじれる(しなる)”ことで、
空力性能が最適化するように設計することが、
FRPを用いた空力特性を重視する構造設計でも良く行われます。
旅客機でも最近の主翼にはウィングレットという先端の小さな突起物がなく、
飛行中の主翼の”ねじれ”や”しなり”によって空力特性を最適化しています。
主翼先端は乱流が起こりやすく、それが損失となるためにウィングレットをつけていましたが、
”主翼そのものの変形”で最適な形状になるよう、
異方性も考慮しながら主翼剛性を調整しているのです。
このような狙い通りの変形をさせるにあたって適用材料をFRPにした場合、
異方性を考慮した積層設計は不可欠でしょう。
長期運用には構造材料自身にセンシング能力を持たせることが肝要でFRPは当該アプローチに向いている
HAPSは長期運用が求められる動的インフラとの認識です。
冒頭のSoftbankの動画では数カ月にわたって継続運用と述べられていますが、
できればより長く継続運用できることが望ましいでしょう。
電波基地として用いる場合、最も故障のリスクが大きいのは通信機器そのものだと考えますが、
主翼である構造部材の損傷リスクも無視できません。
後者のリスクに対しては、構造材料損傷の前兆を速やかに捉えるセンシングの考え方が重要であり、
FRPを主構造として用いる場合、比較的相性がいいと考えられます。
FRPは複合材料であり積層工程が存在
FRPはそもそも繊維と樹脂を組み合わせた複合材料です。
しかも前述の通りそれを積み重ねるという”積層”があります。
これらの工程にセンシング効果のある導線やセンサを導入することは、
他の材料と比べて容易といえます。
FRPは初期損傷の場合、固有の周波数帯を伴う”音(振動)”を出します。
これを検知し、部品の交換を促すといったことはその一例です。
圧電素子や光ファイバなどが代表例で、
過去にも何度かFRPのセンシングについてはご紹介したことがあります。
※関連コラム
無人であっても空を飛ばす以上、型式証明は必要
やはり無視できないのが型式証明でしょう。
たとえ無人であっても万が一墜落することがあれば、
地上に危険に及ぶことを考えれば当然とも言えます。
さらに軽量化を目的に、航空機業界では最も信頼が無い材料の一つであるFRPを使う以上、
相応の型式証明に関する要求が課されるものと考えられます。
この辺りはAAM(空飛ぶ車など)を引き合いに過去に詳細を述べたことがありますので、
そちらを合わせてご参照ください。
※関連コラム
Advanced Air Mobility(AAM)の概況と構造材に用いられるFRP部品の型式証明
まとめ
HAPSはこれから様々なところで途切れることのない通信網を構築するにあたり、
重要な役割を果たす可能性が高まっています。
元々は音声や画像に関する高速通信として用いられてきた5Gの通信網を、
AAMをはじめとしたAir Taxiの情報通信に活用できないかという検証実験が始まっています。
地上の基地と航空機の通信機とのやり取りを通じて、
建物やプロペラの存在によるデータ通信状態変化を含む検証実験が行われ、
4から8GHzというC-Band Radioという周波数帯を活用した通信機器で、
AAMに5Gが活用できるかの検証を継続するとのことです。
※参考情報
NASA Tests 5G-Based Aviation Network to Boost Air Taxi Connectivity
5GがAAMにも活用されるとなると、
今まで以上に途切れにくい通信環境の構築が必要となり、
そこでは地上障害物の影響を受けないHAPSが重要な役割を果たすかもしれません。
バッテリやモータの性能向上はもちろんですが、
FRPを活用した構造設計が進化すれば、
年単位での長期飛行が長期飛行が可能なHAPSが実現できるでしょう。
そして運用を終えたHAPSを確実に回収し、
劣化したバッテリや損傷した構造物を交換し、
再利用するといった持続可能な運用に関する考え方を忘れてはいけません。