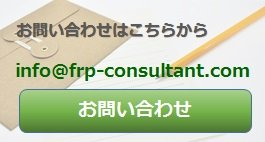FRP戦略コラム-ガラス繊維強化プラスチックによる怪我抑制に関する技術的対応
本コラムでは、ガラス繊維強化プラスチックによる怪我抑制に関する技術的対応について述べたいと思います。
国民生活センターから発出されたガラス繊維強化プラスチックに関する注意喚起
2025年9月17日に、国民生活センターからガラス繊維強化プラスチックによる怪我に関する注意喚起がなされました。
※参考情報
ガラス繊維強化プラスチックによるけがに注意!-傘の骨などに使用されています-(国民生活センター)
以下、本注意喚起内容に関連する技術的要点を述べ、ガラス繊維強化プラスチックによるけが抑制に関する技術的対応について述べたいと思います。
対象となっているのはFRPのうちガラス繊維強化プラスチックのGFRP
注意喚起の対象となっている材料は、FRPのうちガラス繊維で強化されたGFRPです。
複合材料はかなり広域な材料定義となりますが、その中で強化繊維とマトリックス樹脂で組み合わされた材料を総称してFRP(Fiber Reinforced Plastics)と言います。
強化繊維
強化繊維は主として無機繊維と有機繊維があり、一般的には無機繊維、特に今回対象となっているガラス繊維が圧倒的なシェアを誇っています。
無機繊維としては他に炭素繊維、アルミナ、ボロン、ウィスカなどもあります。
有機繊維も一定数あり、高機能のアラミド繊維やポリエステル繊維がその一例です。
最近は天然資源活用の観点から、生物由来の有機繊維活用の取り組みも始まっています。
マトリックス樹脂
FRPとして組み合わせるマトリックス樹脂には大きく分けて熱をかけて固める熱硬化性樹脂と、熱をかけて溶融させたうえで再度冷却して固める熱可塑性樹脂があります。
FRPとして最も多く使われていると考えられるのは熱硬化性樹脂だと不飽和ポリエステル、熱可塑性樹脂だとポリプロピレンです。前者の樹脂に組み合わせるのはチョップドストランドマット、後者の樹脂に組み合わせるのは、繊維長が数mm以下の短いガラス繊維で、フィラーのような扱いです。熱硬化性樹脂には他にビニルエステルやエポキシ、熱可塑性樹脂だとポリアミドなどがあります。
今回注意喚起されているような、テントや傘の骨組みに使われているのは、成型体の形状を考慮すると一般的には連続繊維形態のガラス繊維(ロービング。詳細後述。)に、不飽和ポリエステル含浸させたFRPであると考えます。
※関連コラム
パイナップルの葉を 3D printing 向けの強化繊維に適用
FRP戦略コラム – FRPのマトリックスは熱硬化性樹脂か熱可塑性樹脂か
ガラス繊維の形態
ガラス繊維はロービングと呼ばれる、複数のガラス繊維が束になった状態が主たる材料の状態です。
それ以外にはガラスウールもありますが、FRPではあまり使われません。
ガラスウールとロービングの外観の違いについては、以下のようなサイトの画像を見ていただくと理解いただけるかと思います。
画像中、長繊維と書かれているのがロービング(ガラスロービング)のイメージになります。
※参考情報
今回、注意喚起されているガラス繊維はロービングと呼ばれる状態であることをご理解ください。
ロービングは数μmから数十μmの細いガラス繊維を束ねたものです。これが後述する問題に関係します。
長尺物をFRPで作るのは引き抜き成型が一般的
国民生活センターの喚起内容を見ると、対象としているFRP製品は傘やテントの骨組みといった、長尺のものが多いようです。
このような一定の断面形状を有する製品の長尺成型には、通常”引き抜き成型(成形と表記することもあり)”と呼ばれるものが適用されます。
引き抜き成型はその名の通り、強化繊維(ガラス繊維の場合はロービング)を引張りながら金型内を通し、その金型内に樹脂を流し込んで、金型から出てくるときは樹脂が含浸した状態のFRPが連続的に出てくるというものです。
詳細は過去のコラムをご覧ください。
※関連コラム
FRP製品で生じた問題は樹脂で強化されたガラス繊維が”刺さる”こと
今回問題とされているのは、一言でいうと”刺さる”という事象です。
冒頭の国民生活センターの動画でも触れられていましたが、屈曲や表面の損傷、切断といった事象でガラス繊維が表面に露出し、場合によっては破断したガラス繊維が人の手に刺さったとあります。
ガラス繊維を含む無機繊維は”屈曲”つまり、曲げられることに対してあまり強くありません。
機械・物理特性の非常に高い無機繊維である炭素繊維も同様です。
強化繊維は
引張られること
に対して耐えることを想定して作られているものだからです。曲げには強くないのです。
そして、屈曲や破断、破損したFRPに触れてしまうと、
FRP内の損傷したガラス繊維が露出して刺さることがあります。
繊維単体だと”チクチクする”、”かゆくなる”という現象が主となりますが、
FRPの状態で繊維端部が露出すると、その繊維がマトリックス樹脂で被覆されることで強化されているため、
当該繊維が繊維単体の時より剛直(硬いこと)になり、
より刺さりやすくなるのです。
今回、怪我として認識されている事象を引き起こしているのはガラス繊維単体だけでなく、
樹脂と一体化した剛直なFRPが刺さり、出血するような怪我につながってしまったと考えます。
今回のような問題を抑制するため、技術的な対応は何かできないかについて専門家の観点から述べます。
最外層を有機繊維で被覆するのが定石
これは複合材料設計では常識との認識ですが、無機系の硬い繊維を強化繊維に用いる場合、人と触れるFRP製品は最外層を有機繊維にします。
有機系の強化繊維は無機系のそれと比べて柔らかく、屈曲にも強いため、
材料自体が損傷しても刺さる可能性を低減できるからです。
仮に損傷などをして無機系の強化繊維(例:ガラス繊維)が露出する可能性が出たとしても、最外層が有機繊維であればそれが無機系の強化繊維を外側から抑え込むことで、直接接触することを防ぐというイメージとなります。
高速移動が主で、人との接触も不可避なレース車両などではこのような対策をします。
FRPが前出の複合材料という組み合わせに自由度がある故、可能な対応といえるでしょう。
引き抜き成型で外側だけを有機繊維にするのは簡単ではない
定石の対策は前述の通りです。
これは工程がハンドレイアップという手作業で強化繊維を重ねていく場合は難しくない一方、今回のような長尺製品を作る引き抜き成型で最外層を有機繊維にするのはそれほど簡単なことではありません。
引き抜き成型の金型は入り口と出口の寸法は違うことが一般的で、広い入り口から強化繊維を引き入れ、金型内でマトリックス樹脂を含浸させた後、出口側を狭くすることで型内の圧力を高め、マトリックス樹脂の含浸と外側の形状成型を行っています。
仮に外側を有機繊維にすると、無機繊維と比べて一般的に摩擦抵抗が大きくなる上、
当該繊維と比べて弾性率や強度が低いことが多いため出口付近で繊維が切れる、
摩擦が大きすぎて樹脂の硬化が進み”焼ける(樹脂の硬化が早く進みすぎる)”、
有機繊維が長手方向に大きく引き伸ばされる等の問題が生じる可能性もあります。
後工程で被覆するのも一案
例えば長尺ものであれば、成型した後にゲルコートをはじめとした樹脂等でコーティングを行うというのも一案です。
ここでいうコーティングで重要なのはFRPときちんと一体化していること、そしてゴム弾性を有し、ある程度の変形に追従できることでしょう。
引き抜き成型後の成形体に、スプレー法などで外層をコーティングするのが一案です。当然膜厚管理をするといった工程制御を行わないと、テントや傘といった細径のものだとはまらない、といった問題も出るため注意が必要です。
※関連コラム
それ以外だとワイヤハーネスの要領で、最外層を薄いテープで被覆するという手もあります。
以下の動画のイメージです。
これはコーティングよりも最外層の厚み制御がやりやすいというメリットはありますが、それでも寸法精度やコストといった問題も出る可能性はあります。
ただこのような”最外層を新たに形成し、強化繊維が内部から出てくる可能性を抑制する”という設計思想を取り入れ、
課題解決に向けた対応を検討することは必要だと考えます。
最後に
FRPが原因で怪我をされた方が出ていることは、大変残念なことです。
コストや納期ばかりを注視して、設計や品質管理が不十分だったことが原因だとすれば、絶対に回避しなければならないことでしょう。
今回ご紹介したように、FRPの特性をきちんと理解して設計を行えば、リスクはゼロにできなくとも低減させることは可能です。
怪我をするようなものはだめだといって使用しないということではなく、生じた問題や課題と真摯に向き合い、技術的に解決しようとする姿勢が重要だと考えます。