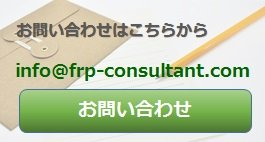FRPのRepairに注目するiLAuNCH Trailblazer programと当該工程の要点
オーストラリアではiLAuNCH Trailblazer programと呼ばれる、
主に航空宇宙産業を想定した産学連携の現在進行中の取り組みがあります。
ここでは様々なテーマがあり、例えば以下の動画は農業に関するものです。
画像技術とそれを応用した模擬太陽光による植物の生育を研究し、
地球外での自給自足を目指している趣旨の取り組みが述べられています。
iLAuNCH Trailblazer programではFRPのRepairに関するテーマも存在
同プログラムの中ではFRP関係のものもあります。
その一つがFRP repair processの最適化に向け、
3DEXPERIENCE platformを基本としたシミュレーション、
さらには非破壊検査や補修といった実工程のリンク付けを行うという取り組みです。
損傷を受けたFRPの非破壊検査結果からトポロジ(またはトポロジー)を生成してCADモデルに直接落とし込むことで、具体的に形状物のどの個所で剥離等の損傷が見られるかについて可視化することで、当該補修工程の最低化を行うというのはその一例です。
ここでいうトポロジとは”要素の接続に関する情報”とのことです。
※参考情報
iLAuNCH Trailblazer programに参加しているのは、
ソフトを提供するDassault Systemes、航空機関連の産業界からはMemko、
そして学術界からはUniversity of Southern Queenslandです。
※参考情報
Transforming Composite Material Repair in Aviation
この取り組みでは多くのソフトを使用
使用しているソフトのプラットフォームは3DEXPERIENCE platformですが、
検証要素ごとに異なるソフトを用いており、
かなり大掛かりな取り組みである印象です。
例えばモデリングを行うCATIAと有限要素法によるシミュレーションを行うSIMULIAをループさせ、FRPのRepairについてより効率的な手法と形状を定義することを行っている、といった記述が前出の参考情報に見られます。
より具体的にはRepairを行うべき箇所の構造的特徴(恐らく形状や生じうる応力等)を踏まえ、
Repairに用いるパッチ材(Repair向けに切り出した強化繊維に樹脂を含浸したプリプレグシートのこと)の形状と厚みを決める、
という計算がなされているようです。
この結果を最終的には3DEXPERIENCE platformに集約し、
できる限り不必要な材料を追加せず、
かつ製品が元々有している特性を変化を最小化させたRepairを提案することに狙いがあると述べられています。
これ以外にも損傷個所をどのような工程手順で除去すればいいかを予想するDELMIA、
補修個所の温度と材料の硬化状態を比較するENOVIA、
FW(Filament Winging)について実工程での画像をリアルタイムで取り込み、
形状と工程の最適化とRepair工程の品質向上を目指すvirtual twinもあります。
FRPのRepairを想定するのには構造物を安全かつ長期間使いたいという狙いがある
何故FRPのRepairがiLAuNCH Trailblazer programで取り上げられたのか。
その理由は、恐らくですが
「FRPのRepairを想定するのは構造物を安全かつできるだけ長期間使いたい」
というニーズの存在故だと考えています。
航空機業界はもちろん、宇宙業界はさらに切実だと思いますが、
仮に輸送船等何かしらの構造部材に損傷が見つかった場合、
新しいものをすぐに作るというわけにはいかず、
ぞれ故 Repair という考え方が重要になると考えます。
部品製造はもとより、そもそも原材料がすぐ手元にあるという状態が当たり前ではないからです。
宇宙での長期滞在を実現する支援インフラの一つとして3D printingが注目されているのも、
現地で様々なものを作れるという柔軟性が念頭にあります。
※関連コラム
Artemis計画での月面基地製造に適用検討が進む 3D printing
FRP Repairのポイントには知られていないことも多い
iLAuNCH Trailblazer programでも注目されるFRP Repairですが、
本工程の要点についてあまり知られていないかもしれません。
以降、FRP Repair向けのツールを販売する企業の動画も参考に、
技術的に重要と思われる点を中心にご紹介したいと思います。
FRP Repairに特化した工具
今回参考にしたのはdark matter composites ltdのStep Sanding Tool Kitsというものです。
以下のページで概要が述べられています。
※参考情報
Step Sanding Tool Kits/dark matter composites ltd
自分自身はこれを使ったことはありませんが、
本工具については使い方に関する動画が複数公開されており、
これを見ていくことで一般的なFRP Repairの要点の一つである研磨除去に触れることができます。
以下、順にご紹介します。
FRP Repairでは不可避な損傷部の研磨除去に伴う粉じん発生の抑制
以下の動画がStep Sanding Tool Kitsの概要に関するものです。
FRP Repairの基本は損傷部の研磨除去にあり、
その際に発生する粉塵が問題である一方、
当該工具だと集塵機能も付与されているため作業環境の改善につながると述べられています。
上記の動画でも紹介されている作業説明動画を見ていくと、
本工具がFRP Repairという観点で大変よく考えられているものであるとわかります。
回転研磨刃物の高さ位置を自由に変えられる
以下の動画はSurface Diamond Planer、
つまりダイアモンドバイトのついた回転平面研磨刃物を、
回転工具に取り付ける工程を見せながら、
当該工具の基本構造を説明しています。
工具先端につけられた円盤型のものがSurface Diamond Planerです。
加工対象によっていくつかのグレードがあることは、
上記一連動画のSection 1で触れられています。
ナットから25mm位置で固定するなど、円盤の軸位置の設定が述べられていますが、
このような刃物の位置設定がFRP Repairでは大変重要です。
本点については詳細を後述します。
研磨する領域を厳密に制限
円盤形の治具に取り付けることで、
規定した円周軌跡での加工ができるようにしていることが分かります。
これはFRP Repairにおいて、
「不必要な領域の研磨除去を行わない」
という重要な観点によるものです。
FRP Repairにおいては損傷個所を除去することが求められますが、
除去することによりマトリックス樹脂だけでなく、
何より強化繊維の連続性が失われます。
この不連続領域を最小化するのはFRP Repairでは不可避の考え方であり、
それ故、研磨除去する領域をいかに最小化するかを実現するため、
このような治具を用いていることをご理解ください。
iLAuNCH Trailblazer programのご紹介のところでも述べましたが、
補修領域の最適化、より具体的には必要最低限の領域に補修範囲を抑えることが肝要です。
当該programでは非破壊検査結果をモデルに落とし込んだのも、
本観点が念頭にあります。
定盤の上で刃物の表面をゼロ点に調整
前出の治具に取り付けた工具を常磐の上に載せ、
刃物が治具の底面と面一になるよう調整しているのが以下の動画です。
ロックナットを緩めて工具を上から見て時計回りに回すと刃物が治具の底面に対して下がり、
反時計回りに回せばその逆となります。
ゼロ点調整ができたら、再度ロックナットを固定します。
FRP Repairに向けた層間方向の削り量を調整
以下の動画を見ると、工具に取り付けられた目盛りを見ながら、
どのくらい刃物を治具の底面部から下げるか、
つまり削り量をどのくらいにするのかを調整している様子が確認できます。
動画中ではロックナットを緩めて治具本体を上から見て時計回りに1回転させるごとに、
1.5mmだけ刃物の位置が下りてくると述べられています。
またロックナットのすぐ上にある回転部の金属部には規則的な黒色の着色がなされており、
この幅だけ回転させることで0.05mm分、刃物位置を上下できるとのこと。
治具に付属の目盛りを使って初期位置をマジックなどで記載すれば、
理屈でいえば厚み0.05mm刻みで削り量を調整できることとなります。
削り量を調整しながら損傷個所が無くなるまで研磨除去
実際に少しずつ研磨除去の量を調整していく様子は、
以下で見ることができます。
対象としているのはゲルコート付きのGFRPです。
最初はゲルコートのみが削れたレベルですが、
徐々にGFRPが見えてきています。
最終的には目視で損傷個所が無くなるまで削り量を増やしています。
※関連コラム
曲面を有する場合は柔軟性のある治具で加工領域を指定
FRP Repairをしたい領域は平面とは限りません。
以下の動画ではなだらかな曲面を有するCFRPを、
柔軟性のある治具を用いて規定領域を研磨除去している様子を確認できます。
損傷個所除去後は補修用材料を積層の上、再硬化
dark matter composites ltdの動画では損傷個所の研磨除去までしか動画がありませんが、
その後は除去した箇所に補修用FRP材料を適用し、加熱硬化するのが通常のFRP Repairです。
オートクレーブ、オーブン、または局所加熱させる場合があります。
以下は一例です。
この動画ではいずれも減圧してバックで押し付けることで材料を加圧し、
そのまま硬化させています。
もしハニカムサンドイッチ構造等の場合は、
同様にハニカムを入れる、必要に応じてフィリングコンパウンドを入れるなどして空間を埋め、
そのうえで補修用のFRPを載せて硬化させます。
※関連コラム
ここまでFRP repairの要点について述べてきました。
最後に関連して知っておきたいことについて述べておきます。
FRPの補修は必ずしも正義ではない
FRP Repairの必要性を紹介しておきながら矛盾するような内容かもしれませんが、
個人的にはFRPの補修はかなり適切に行わないと”危険”と考えています。
その理由はシンプルで、この前にも少し触れましたが
「強化繊維と樹脂の連続性が失われるから」
です。
材料の連続性が失われるのは、FRP設計の観点から言うと致命的な変化点です。
仮に補修材として用いたものが母材と同じ組成の材料であっても、
後工程で硬化させるという”大きな時間差が生じている工程”で製作されたFRPには、
必ず”界面”が存在するからです。
この界面は複合材料としての特性発現には負の側面しかなく、
破壊起点になりうることは容易に想像できます。
基本的には補修が不要になるよう工程を最適化する、そして何より、
「不必要に厳しい技術要件をFRP構造部材に適用しない」
という柔軟な発想が必要でしょう。
多少の欠陥や損傷があっても簡単には壊れないよう、
形状や積層配向、部品保持条件設定の際は不要な荷重負荷にならないよう配慮するといった、
設計的な観点が必要です。
業界的にもこのような考え方を有する設計者の増加が望まれているに違いありません。
なお、無理なRepair(Reworkは別:詳細後述)を行うくらいであれば廃棄すべき、
というのが私個人の考えです。
大きいものを小さくする研磨補修は容認できる
一方で容認しやすい補修(Repairではなく、Reworkのイメージ:詳細後述)は、
「大きなものを小さくする」
という引き算に関するものです。
これは実際に行っても前述のような複合材料の連続性は失われないことが一般的であり、
設計的にはあまり懸念が無いからです。
そのため、今回ご紹介したような丁寧に設計された治具を用いて、
丁寧に加工できる前提であれば、
ニアネットに作ることにこだわらず、
少し大きめに作って追加工するという考えが結果的に量産に対しては近道である可能性もあります。
もちろん加工においてはFRPを損傷させないよう、
刃物や送り速度などの加工条件を最適化することは前提となります。
”大量生産を想定した場合、そのような追加工は絶対に許容できない”という意見もいまだに見聞きしますが、
そもそもそのような量を追うような取り組みに対しては、
短繊維と熱可塑性樹脂を組み合わせた射出成型品を除き、
FRPは基本不向きであることをそろそろ一般常識として認識してほしいと私は考えています。
※関連コラム
FRPの高品質、かつ高速での加工を実現するHufschmiedのT-Rex(R) tool
RepairとReworkは違う
FRPについて英語でいうRepairとReworkはどちらも同じような意味と認識されるかもしれませんが、
私の居た航空機業界では少なくとも全くの別物です。
Repairというのはかなり大掛かりなイメージで補修というよりも改造といったニュアンスです。
航空機業界では認められることは少なく、主翼や胴体など大型構造物に限りやむを得ず認める、
といった印象です。
それに比べてReworkというのは、前述の通り大きなものを少し削るといったものを意味しています。
これらの違いに関する明確化は難しいところですが、私の理解では
- Repair:当該工程前後で性能に変化がみられる
- Rework:当該工程前後で性能に変化が無い
です。
分かりにくいと思いましたので、もう少しそれぞれについて私の考えを述べます。
FRP repairのイメージ
FRPのRepairはその工程によって複合材料の連続性が失われている以上、
全く同性能というわけではない。
しかし、既存構造物等への損傷を最小化した適切な研磨除去を行い、
また機能再生に必要な補修材を適切な工程で用いて形状を復元しているため、
製品に求められる最低要件は満たしていると考える。
上記のイメージです。
FRP reworkのイメージ
FRPのReworkは元となる複合材料の構造に損傷等は与えておらず、
力学的に無関係な箇所への材料塗布や、
余剰分の材料除去に限る。
すなわち、本工程前後において製品性能への影響はなく、
結果として問題なく最低要件は満たしていると判断できる。
このような解釈でしょう。
最後に
今回はFRP repairについてiLAuNCH Trailblazer programの概要、
並びに工程に用いるStep Sanding Tool Kitsを例にRepair工程の要点、
さらにはそれらを踏まえて理解しておくべき観点について触れました。
このような考え方は、FRPを用いた製品の拡大には不可欠な考えです。
製造時は歩留まりを上げ、市場に出回った後も長く使うための必要条件だからです。
個人的な意見として手先の器用な方の多い日本では、
FRP RepairやReworkは向いていると考えます。
一方で日本企業の方は先に行き過ぎて、
本来やらなくては良いことまで先回りしてしまうことで、
結果的に技術的な問題を生じさせるということがあるのも事実です。
いずれにしても今後、FRP repairやreworkを進化させるためにも、
適切な技術要件や工程を考えられる設計者の育成が急務であり、
それが結果としてFRPを用いた製品の拡大につながると考えます。
もしかすると、FRP repairやreworkが最も浸透している業界の一つは、
サーフィンを筆頭としたマリンスポーツであり、
そこに関連する方々の方がこの辺りの感覚をお持ちかもしれません。