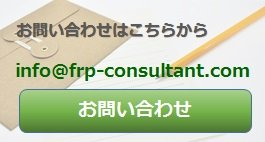CFRPとNi/Ag/Ni膜界面でClイオンによって生じる腐食に関する研究
今回はCFRPの表層に、PVD(Physical Vapor Deposition)によって生成されたNi/Ag/Ni膜とCFRP間で生じる腐食に関する研究についてご紹介したいと思います。
参照した学術論文について
参照した学術論文(以下、論文)は以下のものです。
Polymer Journalは有償購読が基本ですが、本論文はOpen Accessですのでどなたでも読むことができます。
私がインターネットの恩恵を感じるのはこのような時です。
ご存じな方もいるかと思いますが、
査読結果で掲載許可の判断が出たのちにFirst AuthorがOpen Accessを望み、
かつ必要とされる費用を払えばOpen Accessにしてもらえます。
私も執筆した論文の1報だけは当時勤務していた企業がOpen Accessへの変更を許可してくれたため、
自由に読んでいただける状態です。今でも引用数が地道に増えているのはそのおかげかもしれません。
別の論文についても査読終了後に当時の管理部門にOpen Accessにすることを相談したものの、
予算が無くてだめでした。
安い金額ではないということです。
つまり上記の筆者もお金を払ってOpen Accessにしてくれていることになります。
執筆した研究者は
「自分の研究をより広めてもらい、学術業界の発展に貢献したい」
と考えている可能性もあり、その好意にあずかっているといえるでしょう。
もちろん、実情は異なるかもしれませんが本来の論文の意義はここにあると私は考えています。
論文の概要
この論文の要点について抜粋して述べたいと思います。
論文の目的
一文でいえば、
「CFRP上にPVDで生成されたNi/Ag/Niの金属膜について、
酸性状態でClイオン(塩化物イオン)を含む水溶液に暴露された際に生じるCFRP/金属膜での、
当該膜の剥離を伴う腐食のメカニズムを明らかにする」
となります。
腐食性水溶液に暴露されることで金属膜表層に腐食が生じるのはイメージしやすいですが、
金属膜とCFRPの界面でも顕著な腐食が生じることに疑問を感じた方も多いかと思います。
本観点を念頭に何が起こっているのかを明らかにするというのが論文の目的にあります。
なお、論文中ではEpoxyと金属膜間の腐食という表現ですが、
実際に評価している材料はEpoxyをマトリックスとしたCFRPであるため、
以降でも母材はCFRPとして話を進めたいと思います。
評価対象
母材
評価に用いる母材はCFRPで、強化繊維はT700、M40との記述があります。
どちらも東レ製だと思いますが、論文中で前者は三菱、後者は東邦テナックスと書かれていました。
マトリックス樹脂は2207BというWeihai Lante Compositeという中国企業のものとのこと。
細かい含浸、成型方法は記載されていませんでしたが、
連続繊維をそのままWetで含浸させ、
0.18mm厚み程度のCFRPを作ったとのことです。
繊維が何故2種類あるのかはわかりませんが、
薄板のCFRPとして成型したことだけはいえそうです。
恐らく今回の評価において炭素繊維種はあまり大きな影響を与えないと考えられますが、
不明となっているVf(RC)や積層構成は無視できないため、
本来はこの辺りの詳細情報は欲しいところです。
CFRPのコーティング
既述の通り蒸着であるPVDで行っています。
Ni/Ag/Niの3層ですが、それぞれ厚みは50-70μm、450-600μm、130-170μmとのこと。
CFRPと接触するのは50-70μm厚みのNi層です。
PVDは主に「真空蒸着」「スパッタリング」「イオンプレーティング」があるようですが、
具体的にどれを用いたのかは不明です。
※参考情報
今回は複数金属種の3層構造であること、
膜厚制御が重要であることを考えると、
PVDに関する参考情報からArを用いたスパッタリングであると考えます。
上記のようにCFRPをPVDにより表層に金属膜でコーティングをしたものが、
今回の評価対象となっています。
腐食評価溶液
SS(Salt spray:塩水噴霧)とAAS(Acidic artificial sweat:人工汗液 酸性)を用いています。
SSについてはCB/T 2423.17-2008、AASについてはISO 3160-2に詳細記述があるとのこと。
前者は中国の規格です。
ISO 3160-2の詳細はWeb上では見られませんでしたが、
この規格そのものは
「Watch-cases and accessories — Gold alloy coverings
Part 2: Determination of fineness, thickness, corrosion resistance and adhesion」
とのことで、金メッキの外観に加え、耐腐食性や密着性を評価するもののようです。
ただし、この規格に準ずるAASは製品として存在しており、
購入することも可能です。
※参照情報
Artificial Sweat, ISO-3160-2(Reagents)
SSは塩化ナトリウムの5%水溶液であり、pHは6.5-7.2の中性域に調整されています。
塩水噴霧の条件は35℃環境で、1-2mL/80cm2・hとのことです。
一方でAASの場合は金属膜で被覆されたCFRPをAASで湿らせた布で覆う、
という形で暴露しています。
AASのpHは4.6、そして上記の暴露環境の温度は55℃、湿度は93%です。
金属膜のCFRPとの密着性はクロスカットで評価
金属膜の母材であるCFRPへの密着性はクロスカット試験で評価しています。
当該試験には規格があり、ASTM D3359はその一例です。
以下の動画をご覧いただくと、試験の概要をご理解いただけるかと思います。
母材との密着性が低いと、表層の膜が剥離します。
密着界面の形態や元素分布はAFM、SEM/EDS、XPS、PiFMで評価
分析はかなり丁寧に行っています。
それぞれについて、分析の概要について述べます。
AFM
形態の分析にはAFMを使っています。
原子間力をカンチレバーで検知するAFMは、原子レベルでその形態を把握することができます。
例えば劣化前後で金属膜の断面をAFMで確認することで、
CFRPと金属膜間で剥離が生じていることを明らかにしています。
SEM/EDS
試料に電子線を照射し、結果として発生する二次電子や反射電子を計測して、
観察平面の凹凸や形態を観察します。
CFRPと金属膜のサンプルの断面についてSEM観察することで、
Ni/Ag/Niの3層構造形態がどのように変化したかを画像によって示しています。
また上記で発生するもののうちX線に着眼し、
X線エネルギー分散型の分析器で計測するのがEDSです。
これは入射したX線のエネルギーの一部を吸収し、
また構成元素固有の波長をもったX線が生じることを応用した元素分析手法です。
EDSは評価面近傍のみの評価であり、深さ方向の情報はあまりとれません。
本論文では特に腐食状況理解のキーとなるClの分布について本分析を用いています。
XPS
入射した光子エネルギー(hν)から固体の仕事関数(φ)と、
測定運動エネルギー(Ek)を差し引いたものと結合エネルギー(Eb)は等しいという、
以下のアインシュタインの光電方程式の関係から結合エネルギーを算出できます。
Eb=hν-φ-Ek
仕事関数は固体表面から電子を取り出す最小のエネルギーであり、
その値が既知の元素であることも多く、また光電子の最大/最小エネルギー差から計測値として求めることができます。
※参考情報
結果、結合エネルギーを算出することができ、かつこれは元素由来の固有の値となります。
つまりどのような元素構成であるかをXPSによって明らかにすることができます。
今回の評価ではAlKαという軟X線を光源とし、
60°の角度から照射しています。
さらにArによるエッチング(表面元素除去)を行えるようにすることで、
深さ方向の元素構成を評価しています。
XPSは主に金属層の深さ方向の元素構成比評価に用いられており、
腐食によるNi層の大幅な減少を明らかにしています。
PiFM
PiFMはPhoto-induced force microscopeの意味で、光誘起力顕微鏡と呼ばれるようです。
前出のAFMによる原子間力と波長可変のレーザ光照射による励起応答を同時計測し、
形態と元素の分布を可視化する分析技術と理解しました。
ここでいうレーザー光照射による励起応答は、FT-IRと同等であると考えます。
例えば以下のPiFM適用例では、
ガラス基材の上にアミノシランでコーティングする際に生じる被膜不均一化の問題について、
PiFMを用いて原因究明しています(Case Study 1: Aminosilane Glass Functionalization)。
※参考情報
前半ではガラス基材をそのまま評価し、局所的に厚みの異なる個所があること、
そしてその該当箇所には2941、2869cm-1のCH伸縮運動、
さらには1400cm-1以下のCH曲げ運動にそれぞれ帰属されるピークが認められることから、
有機物由来の汚染が被膜不均一化の一因であるという主張がなされています。
同様にアミノシランでコーティングしたのちに同様の分析を行っています。
SiORやSiOSiに帰属されると考えられる1060cm-1、
そして脂肪族アミン、芳香族アミン構造に帰属されるアミノシラン由来と考えられる1623、1678 cm−1で評価し、
アミノシランが局所的に凝集している様子をとらえ、
これも膜不均一化の要因であることを示しています。
今回ご紹介している論文において、
PiFMは特にCFRPと金属膜境界における形態に加え、
元素分布勾配の評価に用いています。
次に結果のポイントを述べます。
腐食状況のSSとAASの違い
両者はかなり異なる結果となっています。
AASに暴露されると明確な剥離がCFRP/金属膜間に発生
論文中のFig.2に様子が示されています。
冷静に考えると大変不思議ですが、
AAS暴露のケースのみ、CFRP/金属膜の界面付近に0.4μm程度の幅で剥離が認められています。
そしてこの剥離が生じた金属膜は、
クロスカット試験でもCFRPから簡単にはがれることが明らかとなっています。
SSとAASの腐食の様子は形態と構成元素比率で明確な差がある
最もわかりやすいのは論文中のFig.3で示されたSEM画像でしょう。
腐食前、SSまたはAASによる暴露後の金属膜の様子がそれぞれ示されています。
元々Ni/Ag/Niの3層構造がきれいに見られた金属膜は、
SS暴露だと多少の表層Niの厚み減少が認められるものの顕著な差異はありません。
一方でAASに暴露されたものは層構造が消失しています。
Fig.3(b)の図を見ると金属膜が顆粒状態になっていることが分かりますが、
これは後述するClイオンとAgが反応してAgClが生成するとみられる、
典型的な形態である旨が論文中で述べられています。
さらにEDSの結果から、Ni層が見られない状態であることが示されています。
元素比率の腐食時間による変化はFig.4でグラフ化されており、
SS暴露ではあまり変化がない一方で、
AASでは右肩下がり、つまりNi層の減少が起こっていることが分かります。
硬いNi層の喪失が前述のCFRP/金属膜間の剥離につながったと考えられます。
この元素構成の変化についてはFig.5で示されるXPSの結果からも明らかとなっています。
横軸がエッチング時間、つまり右に行くほど表層から深い領域での評価、
縦軸はそれぞれの元素比率を示しています。
これを見るとAASに暴露されたものは、
まずCFRP/金属膜界面でのNiの減少が認められ、
その後、金属膜全体からNiがほぼ消失している様子が見られます。
腐食の主因の一つともいえるClイオンの浸透について
最後でも触れますが、Clイオンが腐食現象に影響を与えていることが知られているため、
当該イオンの深さ方向をXPSで分析することで、
どのようにClイオンがCFRP内を浸透(移動)するかを調べています。
結果は論文中のFig.6に示されています。
横軸をAASへの暴露時間とした左のグラフを見ていただくと、
青線で示されるNi層の減少に応じて、
黒線のClイオンの存在確率が上昇している様子が捉えられています。
ここにはAFMによるCFRP/金属膜間の剥離(クラック)の最大深さと同幅が赤線で示されており、
Clイオン浸透と比例するように増加しています。
この結果から、ClイオンはCFRP中を浸透し、
その浸透量が増えることに応じて金属膜の腐食と剥離が拡大していることが裏付けられていることから、
当該イオンが腐食促進要素の一つであるといえるでしょう。
論文中で展開されているClイオンによるCFRP/金属膜間の腐食メカニズム
概要は論文中のFig.7で示されています。
高温だとマトリックス樹脂が膨潤しやすいと推測
AASの場合、浸漬温度が高いため(SSは35℃であるのに対し、AASは55℃)、
100℃のTgを有するCFRPマトリックス樹脂が膨潤し、
結果的に架橋間距離が広がってClイオンが浸透しやすくなったのではないか、
というのが主張の一つ目です。
この温度域、含浸時間で膨潤しやすくなるかは疑問ですが、
推測している現象の発生自体は大きく間違えていないでしょう。
酸性環境はClイオンによるNiの腐食を加速と主張
もう一つの主張として、
酸性環境だとClイオンによるNiの腐食が進行しやすいことが過去の論文でも述べられていることを紹介の上で、
既述の通りSSはpHは6.5-7.2、AASは同4.6であることから後者のNi層の当該イオンによる腐食がより促進された、
というのがもう一つの主張のポイントとなっています。
しかしながら本主張を支持するという引用論文はWeb上では見つけられておらず、
私の中では現段階で断定することは難しいと考えます。
殆どのコアジャーナルの情報はWeb上でタイトルを見られることを考えれば、
限られた領域内(学術界、産業界、土地等の意味)での情報と推定されるからです。
ただし、AASによるNiが流出すること自体は確かのようで、
例えば以下のような文献はNiの粒子サイズとAASによるNiの溶出量に関する比較評価を行っています。
よって、NiがAASで溶けること自体は正しい情報といえるでしょう。
※参考情報
CFRP側から浸透したClイオンがCFRP/金属箔界面を腐食
CFRP側から浸透したClイオンが、
金属箔を腐食するというAFMでも認められた事象を引き起こしたとのことです。
水溶液中のClイオン半径はおよそ0.33nmであることが分かっており、
このサイズであればCFRP内を浸透できるのではないか、
ということを論文では言いたいと考えます。
当然温度が高いほうがClイオンの浸透(拡散)速度は高まり、
多くのイオンが界面付近に到達したというのが、
メカニズムの推測と読み解きました。
ただ、肝心要の”何故CFRP/金属膜の界面の腐食が直接AASに接触している面よりも早かったか”について、
明確な記述は認められませんでした。
プライマー層にNi2O3を採用することで界面腐食を抑制できた
これまで述べた腐食の対策として、
CFRPと接触する界面にNi2O3(ニッケル酸化物)を採用することを提案し、
それが腐食抑制に効果が出たと述べられています。
いわゆる絶縁層の設定ですので、
後述する電食を防ぐ効果も期待できます。
最後に本論文について考えるべき点について私の考えを述べます。
CFRP/金属界面での腐食の加速について
前述の通り、CFRP/金属界面での腐食の加速については考察が不足している印象です。
ここについて私が注目したのは、
「Clイオン濃度」
です。
金属膜の外側はAASと常に接触している状態ですが、
常に90%を超える恒湿状態であり、
溶媒である水が飛んでAASのイオン濃度が変化することはあまりないと考えます。
一方で仮にClイオンがCFRP内を拡散、浸透しながら界面に到達した場合、
そのイオン濃度は水溶液状態の外側より高くなる可能性があります。
当然ながらイオンだけが浸透するのではなく、
水分も浸透するので一概には言えませんが、
上記の可能性を考えました。
この可能性を思考的に検証するため、分子サイズに着目しました。
理科年表(2023年度版)を参考に計算します。
水分子のOH間距離はが95.75pmであることから、単純に倍にすると分子サイズ(直径)は0.1915nmでした。
実際は分子内のOH結合間は104.5°の角度があるため2つのH間の距離は0.1514nm(2*95.75*sin(radians(104.5/2))/1000)です。
話をシンプルにするため分子運動や会合するか否かは考えないと、
水分子の最短直径は0.1514nm(水分子を平面で捉えた場合の最小幅のため。ただし、水分子が横向きで浸透することは想定していません。)といえます。
なお、論文中でも述べられていたClイオンサイズは理科年表によると0.334nmでした。
つまり分子サイズだけでいうと、水の方が小さいためよりCFRP内で拡散しやすいといえます。
これだと私の考察は否定されてしまいます。
ただ厳密にいえば、高分子内を拡散するには分子鎖の相互作用も生じるため、
分子サイズだけでは議論しきれない部分もあることは加筆しておきます。
本点については、次に述べる考察でメカニズムの説明ができないかと考えています。
評価資料のサイズと側面からの浸透抑止対策有無と電食の影響
もう一つ今回の評価で気になったのは、
「試験片サイズはどのくらいか、そして側面からの腐食水溶液の浸透抑制対策をしていたか」
です。
今回の腐食評価で採用している浸透試験はいうほど簡単ではなく、
様々な配慮が必要です。
例えば試験片のサイズがあまりにも小さいと、
層間方向だけでなく側面方向からの浸透の影響が大変大きくなります。
そのため、この手の試験では厚みと幅の比率に規定がなされることが一般的であり、
面内の寸法は大きいことが通常求められます。
加えて側面は界面が暴露されている状態のため、
金属テープなどでシーリングするのが一般的です。
側面から腐食水溶液が浸透してしまうと、
層間方向の浸透評価だけでなくなってしまうからです。
この辺りに関する情報は論文中では見られなかったため、
懸念点として示しました。
(もしかすると、Supplementary Informationに含まれるかもしれません)
仮に試験片寸法が小さく、かつ側面の養生をしていなければ、
側面から浸透した腐食性水溶液が界面に早めに浸透した可能性も否定できません。
さらにそこに炭素繊維があれば電食が生じ、
界面の腐食が促進されたという流れであれば、
今回論文で認められた事象の説明の一候補になると考えます。
※関連コラム
最後に
今回はCFRP上にPVDによって生成された金属膜が、
腐食性溶液存在下での長時間暴露でどのような腐食現象を示すのかについて、
複数の視点から検証した論文を紹介しました。
評価そのものは大変丁寧で、参考になった部分も多かったのではないでしょうか。
CFRPに限らず、FRPの多くは異種材と組み合わせて使用することも多く、
これによって生じる界面が問題の起点になることも少なくありません。
このような問題を今回ご紹介したような論文のように、
多角的な視点、特に元素分析を取り入れることは、
現象をより適切に捉えるために重要と考えます。