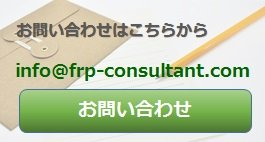ELV指令の改正案から見る炭素繊維の制限への見解
顧問先でも意見を求められる機会が増えてきたことも念頭に、
ELV指令の改正案から見る炭素繊維の制限について概要をご紹介した後、
私見を述べたいと思います。
ELV指令とは

他のWeb情報でもいくつか本点を解説しているものもありますが、
確認の意味も兼ね、自分の言葉で述べてみたいと思います。
参考としたのはELV指令の元情報です。
※参照情報
End-of-Life Vehicles / European Comission
ELVというのはEnd-of-Life Vehiclesの略で、
ELV指令というのはEUが自動車向けの循環型社会実現に向け、
資源の有効活用と環境保護を目指すことを目的とした法令です。
冒頭の部分を自分なりの解釈で述べます。
英文は上記参照情報からの転載となります。
Overview
Every year, over six million vehicles in Europe reach the end of their life and are treated as waste.
When end-of-life vehicles (ELVs) are not properly managed,
they can cause environmental problems and the European economy loses millions of tonnes of materials.The automotive manufacturing industry is among the largest consumers of primary raw materials such as steel,
aluminium, copper, and plastics, but makes little use of recycled materials.
Although the recycling rates of materials from ELVs are generally high,
the scrap metals produced are of low quality and only small amounts of plastic are recycled.
欧州で毎年600万台にも及ぶ廃車については廃棄まで管理すべきで、
環境保護の観点から特に材料についてきちんと考えなければならない。
一次構造材である鉄鋼、アルミ、銅、プラスチックなどはリサイクルが進んできているものの、
まだ再生材の品質の低さや量の少なさという課題がある。
—–
上記のイメージですね。
自動車(想定されているのは二輪車と四輪車だと思います)の廃棄伴う、
材料管理を適切に行い、無駄な廃棄を減らしたいということだと理解しました。
自動車というと四輪車だけをイメージされる方もいますが、
二輪車も自動車であり、その生産台数年間6000万台弱であることから無視できるレベルではないでしょう。
Background
The Directive on end-of-life vehicles (ELV Directive) sets clear targets for ELVs and their components.
It also prohibits the use of hazardous substances when manufacturing new vehicles (especially lead, mercury, cadmium and hexavalent chromium) except in defined exemptions when there are no adequate alternatives.
The exemptions are listed in annex II of the Directive.Since this Directive was introduced, several amendments have been made (for more information, see amendments below).
The EU has also introduced several related rules such as the Directive on the type-approval of motor vehicles regarding their reusability, recyclability and recoverability.A review of the ELV Directive was launched in 2021, resulting in a proposal for a new regulation in 2023.
See the proposed End of Life Vehicles Regulation and clarifications on the proposal, or see the factsheet.
ELVの考え方の中で、有害物質に関する規定も行っている。
鉛、水銀、カドミウム、六価クロムなどの有害物質は代替品が無い場合を除いて使用してはならず、
この方針は材料の再利用や再生を含め電動車などへも適用するよう修正案を示している。
—–
こちらは上記のことを主として述べています。
本有害物質の利用の制限という部分が、
今回話題になっている炭素繊維の使用制限と関連するところになります。
ELV指令自体は相応の長文なので全部を理解するのは大変ですが、
最上位概念についてはご理解いただけたかもしれません。
ではここからは当該指令について、炭素繊維に関わる部分について述べたいと思います。
ELV指令における炭素繊維の言及
こちらについては以下のサイトが最も客観的に事実を伝えていると感じましたので、
それを参考に述べたいと思います。
※参照情報
自動車の炭素繊維は規制されるのか?/ みずほリサーチ&テクノロジーズ
炭素繊維を制限すると明確に記載があったわけではない
大前提として理解すべきはここだと思います。
炭素繊維が登場したのは「ELV規則案(欧州議会改訂案)」(2025年1月29日付け)とのことです。
ここでの記載の方法については、前出の参照情報(みずほリサーチ&テクノロジーズ)にて適切な表現がなされています。
<引用:ここから>
5条第3項において使用の制限には適用除外が存在することを示し、その詳細を従来案附属書III(例:高融点はんだにおける鉛化合物、炭素鋼冷却システムの防食剤としての六価クロム等)で定めている。
さらに5条第4項では、附属書III改訂の権限を欧州委員会に委任している。
(中略)
第2項には、鉛、水銀、カドミウム、六価クロムのみが記載(青字)され、炭素繊維は記載されていない。
その後、第3項で初めて炭素繊維が登場し、合計3か所記載されている。
第2項の使用制限の対象には記載されていないにも関わらず、第3項の適用除外において記載されるという法令としては不思議な構成となっている。
<引用:ここまで>
引用元情報では”不思議な構成”と表現されていますが、
私もまったくの同意見です。
原文によって、上記の事実を私も確認しました。
第2項使用制限という項には書かれていない炭素繊維が、
何故か適用”除外”のところに記載されているのです。
参照情報の考察として述べられていますが、
適用除外に関する要件は決まっていないのに、
名前だけが登場していることで、
「炭素繊維はELV指令で禁止される」
といった拡大解釈による表現として広まったのかもしれません。
いずれにしても5条第2項に炭素繊維が書かれていなかったということは、
有害物質として定義はされていないと解釈するのが普通でしょう。
メディアで当該情報が広がったこともあり、
市場応答(株価変動等)だけでなく様々な業界で懸念を示したのは当然とも言えます。
ただ客観的に捉えた結果、
「炭素繊維を制限すると明確に記載があったわけではない」
という点については理解しておくことが必要だと考えます。
突然湧いて出た炭素繊維への言及は一旦見送りに
これは前出の参照情報にも書かれており、かつ以下のような別の情報源でも言及されていますが、
環境委員会(ENVI)と域内市場・消費者保護委員会(IMCO)の修正案では、
炭素繊維に関する言及はなくなったとのことです。
※参照情報
EU ELV規則案 – 欧州議会の所轄委員会が修正案まとめる、炭素繊維への言及なし/EnviX
後述しますが、FRPを含む複合材料に関する記述も同様の修正がなされています。
複合材料はリサイクルを妨げる材料例として言及されていた
こちらも前出の参照情報でも言及されていましたが、
炭素強化複合材料(恐らくCarbon/Carbon compositeを指したもの。炭素繊維強化複合材料では”ない”ことに注意。)については、材料のリサイクルを妨げるものとして当初提案されていました。
またそれだけでなく、複合材料、繊維強化複合材料(GFRP、CFRPを含む)など、
強化繊維を炭素繊維に限らない幅広い複合材料全体について、
留意すべき材料といった指定にすることが検討されていたこともわかりました。
これらに関連するAnnex IV – Part BとArticle 21 – paragraph 1 – point eの2025年1月時の提案の文言を引用します。
<Annex IV – Part B 引用:ここから>
B FOLLOW-UP AND UPDATE OF THE CIRCULARITY STRATEGY
(中略)
(c) the adoption of design features to
address the challenges posed by the use of
materials and techniques which hamper
easy removal or make recycling very
challenging, for example adhesives,
composite plastics or fibre-reinforced
materials;
<Annex IV – Part B 引用:ここまで>
文の後半にFRPや繊維強化複合材料について、
リサイクルや分別を困難にする材料として言及されています。
これについては、他の項目も含め全体が削除されています。
—
<Article 21 – paragraph 1 – point e 引用:ここから>
(e) the share of materials and
substances preventing a high-quality
recycling process, such as adhesives,
composite plastics, or carbon-reinforced materials
<Article 21 – paragraph 1 – point e 引用:ここまで>
高品質のリサイクルを阻害する材料として、
炭素強化複合材料に言及しています。
こちらはsuch as 以降がすべて削除されました。
また炭素複合材料だけでなく、
接着剤や樹脂をマトリックスとする複合材料という言及もあり、
特に後者はかなり広い範囲になると想像できます。
材料明記、および削除の判断について
Article 21 – paragraph 1 – point eについては、
以下のような判断基準が示されています。
<引用:ここから>
High-quality recycling for technical plastics can be achieved with chemical recycling,
the processes of which are not impacted by the use of the listed materials and substances.
<引用:ここまで>
言及された材料の使用が、リサイクル材料の品質向上には大きな影響を与えず、
仮にこれらの材料が存在しても当該品質でのリサイクルは可能である、
とのことです。
なお、Annex IV – Part Bで削除された項については、
該当する理由は明記されていませんでした。
ここまでの話を踏まえ、どのようなことを考えるべきでしょうか。
FRPに限らず、複合材料がリサイクルしにくいのは事実
今回炭素繊維に関する言及から始まり、
炭素(繊維)強化複合材料全体についても留意すべき材料という認識が、
EUでは存在していることが明らかとなりました。
炭素繊維自体は飛散することによる呼吸器への影響、
といったことがその主張に背景にあるのかもしれませんが、
この辺りは以下のような関連協会でも反論が出されています。
当該参考情報の項目5に繊維径に関する狙い含めて書かれるなど、
私も知らない情報が含まれており勉強になりました。
※参考情報
ELV 指令の修正案に対する意見 / 日本化学繊維協会 炭素繊維協会委員会
FRPを含む複合材料としての視点で物事を見る場合、理解しておくべきは
「複合材料はリサイクルしにくいのは事実」
ということでしょう。
例えば強化繊維の入っていない熱可塑性樹脂であっても、
アロイのような配合が異なるものを使うと、
主となる高分子が同じであってもリサイクルしにくいという話があると聴いたことがあります。
PETボトルのように基本組成が統一されない限り、
材料のリサイクルは簡単ではありません。
このようなリサイクルでは材料組成にデリケートである現実を踏まえると、
そもそも機械的に分離可能な複数の材料で構成される材料が、
リサイクルという観点でいうと難しい材料であることは容易に想像ができるのではないでしょうか。
リサイクルにこだわらず再利用を念頭にした考え方も必要
とはいえFRPを含む複合材料はリサイクルできないとあきらめるわけにもいきません。
Global composite material waste management 2024によると、
FRPを主とした複合材料のリサイクルの割合は重量ベースで4%に過ぎない一方、
同材料の2024年廃棄量(実績)は世界で年間700から800万トンであり、
今後も数%ずつ増加していくと予想されています。
リサイクルはもちろんですが、
過去の連載でも記載した通り、
頑丈な複合材料は”そのまま再利用”、つまり
「Re-useを考える」
ことが、本課題解決に向けた小さいながらも大きな一歩になるかもしれません。
※関連連載
〈連載〉繊維強化プラスチック短信 第4回 天然繊維を用いた熱可塑性プリプレグについて
経済防衛の可能性も示唆されるが推測の域を出ない
確からしさでいえば”わからない”というのが個人的な意見ですが、
日本企業が主導する炭素繊維を狙い撃ちにした、
という言及をしているものもあります。
以下の記事は大変詳細に考察がなされており、
その一部に上述と同様の言及が認められます。
※参考情報
もちろんそのような話は可能性という意味では十分ありえますが、
今の世の中で保護主義的なやり方だけで、
そもそも自国領域の産業を守るという思考が成立するほど単純ではないと考えており、
当該主義はやはり諸刃の剣の意味合いがあると思います。
実際、今回のELV指令についてEU域内でも様々な反対意見が出たという情報にも触れています。
本項の内容についての見解は、推測の域を出ないというところまでにしたいと思います。
炭素繊維以前にガラス繊維の規制に警戒を
何度か述べていますが、
より広い視点から見るとガラス繊維に同様の規制が生じる方が大きな問題になります。
生産量が炭素繊維よりも2桁大きく、
また将来的に出る廃棄物の量も桁違いです。
FRP業界の根幹を担っている基材であるため、
当該業界へのインパクトも相当なものでしょう。
そして過去のコラムでもご紹介した通り、
生体への蓄積も確認されています。
※関連コラム
カキやムール貝の組織内からFRP由来と考えられるGF微細繊維を検出
仮に毒性が無くとも体内蓄積が起こることを問題視され、
自動車業界だけでなく幅広い業界から規制がかかる可能性もゼロではありません。
リサイクルであっても再利用であっても、
ガラス繊維の飛散を防いだ閉鎖系での工程確立や、
実際の用途でも飛散を最小化する使い方、
というものが求められていくのかもしれません。
最後に
ELV指令について調べて分かったことは、
より正確な情報を得るためには複数の情報媒体を比較し、
最終的には元情報を確認しなければならない、
ということでした。
”ELV指令で炭素繊維が有害物質として指定された”という表現を行うメディアもありましたが、
ご紹介した通り事実と異なったことはその一例といえます。
そして、海外の法令は時に産業界にも大きな影響を与えます。
健康と環境保護が重要であることを考えれば、
産業界としても協力すべきでしょう。
見方を変えると技術だけでは乗り越えられない障害が突然生じることは、
決して珍しいことではないのかもしれません。
技術的な軸を持ちながらも、
より柔軟に様々な異業種技術と連携してリスクヘッジをする。
そのような事業戦略が重要なのだと考えます。